目次

週の始めに部下の士気を高めるためのスピーチ
顧客を前にした失敗できないスピーチ
部下の結婚式など大勢の前でのスピーチ
私たちは、規模の大なり小なりあれどスピーチをしなければならない機会は日常で頻繁にやってくるものです。最近はオンラインを通してスピーチする機会もかなり増えました。
たくさんのビジネスマンと関わらせて頂いて感じるのですが、人前で話すことに対して精神的なストレスを抱えて過度の緊張をしてしまう人はとても多いです。
あなたはどうですか?
しかし、しっかりとした心構えや正しい知識そして経験を積めば、スピーチはそれほどほど難しいことではありません。今回は、一度学べば一生使える気持ちの良いスピーチの「コツ」をご紹介します。
はじめまして、この記事を執筆した佐藤政樹と申します。劇団四季出身の研修講師として【受講生を惹きつけながら気づきと学びを促すことをモットー】に、講演会やセミナーの講師だけに限らず大手企業などでさまざまな研修を行っております。人前で話す機会の多いビジネスマンのスピーチトレーニングを多数担当させて頂いております。記事の内容をお読みいただき、もしご興味いただけましたら、ページ最下部のプロフィールや研修内容の詳細をご覧いただけますと幸いです。
1)そもそもスピーチする目的は?
そもそもスピーチする目的は何なのでしょう?デジタル大辞泉では、「対話・演説」と解説しています。「対話」というよりも、一般的なイメージでは「演説・プレゼン」の方がスピーチの印象として強いです。
スピーチは”自分の考え”や”伝える必要”のあることを論理的に構築し、聞き手を「なるほど」と納得させたり共感や感動を生んで聞き手の「心を動かす」ことが主な目的です。
そのためには、事前にスピーチする「目的」や「理由」や「ゴール」を自分自身がしっかりと理解している必要があります。
2)スピーチが変わると人生が変わる?上手になるメリットは?
スピーチをするメリットとは何でしょうか。
一番は自分の考えや伝えたい事と聞き手の心をつなぐ能力が高まり、様々な場面で様々な人と、質の高いコミュニケーションが取れるようになる事です。
日本経済団体連合会(経団連)が毎年行っている新卒者採用アンケート調査では、16年連続で「コミュニケーション能力が特に重要」という結果が出ています。企業が、言葉や文字のやりとりによって自分の考えを正確に伝えることができる人材を求めているということでスピーチ力があがればあなたが社会から必要とされる人材となる可能性も高まるでしょう。
自分の考えを正確に相手に伝え、クライアントの心を動かし共感、賛同してもらうことができれば、その後の信頼関係の構築や仕事の成果へと直結します。
論理的にわかりやすく話す能力を身につけることで、自分自身の頭の中も複雑だったものが整理されたりするものです。
 式典でスピーチをする筆者
式典でスピーチをする筆者
3)スピーチする場面やシチュエーションは様々?
スピーチには、結婚披露宴のようなシチュエーションもありますが、何かの会合に参加した際に急に指名されて大勢の場面で突然話すことになった、などという場面もよく起こります。
先日私も、顧客との懇親会の際に「一言お願いします」と突然ふられて、大勢の前で約3分間のスピーチをしました。
ビジネスの場ではオンライン含めて「3分間朝礼」や「終業夕礼」といった、簡素に1日の目標なり反省点を共有し合う場もありますし、ミーティング後の所感や自分の決意表明を発表する事も頻繁に起こります。
学校行事や地域イベントなど、指名されるかされないかは別として、催し物とスピーチの機会は必ずワンセットと言っていいでしょう。
事前準備ができるシチュエーションと突然振られて話すシチュエーションがあるわけです。
4)緊張するのはなぜ?人前でも緊張しないポイントは?
私はたくさんのビジネスマンにトレーニングをしてきましたが、スピーチする際の緊張で悩まれている方は本当に多いです。
それを裏付けるデータとして「アサヒホールディングス」の行った20歳以上の男女1,579人を対象としたアンケートでは、「とても緊張しやすい」「どちらかというと緊張する」が、全体の8割を超える82.8%でした。
緊張は悪い捉え方をすると自分の持っている能力を妨げる要素です。
「緊張しなければもっとうまくできた」
「緊張して頭が真っ白になった」
「緊張して伝えたいことの半分も伝えられなかった」
本当によく聞く話です。
私は劇団四季時代に年間200回〜250回は舞台に立ち毎回1000名以上の観衆の前で表現をする仕事をしてきました。
この話をすると「佐藤さんは緊張なんてしないんですよね」と多くの方に言われます。
その時、こう答えます。
「そんなことありません。今でも毎回緊張しますよ。」と。
これは本当です。今でも研修前は本当に緊張してしまいます。私は、他の講師仲間と比べて極度の「緊張しい」だと感じます。仲間は私の事を「ビビり」と冗談を言ったりもします(笑)
劇団四季の主役の時は舞台開始の直前は本当に心臓が飛び出そうになる経験をしました。毎回、処刑台に登るような心境でした。
そんな私だから伝えられる今回は私なりの緊張の克服方法とプロの世界の緊張についての考え方をお伝えします。
【大前提】緊張はコントロールできない
緊張は抑えられるものだと思いますか?
最初に残念な話をします。
実は、緊張は自分の意思でコントロールして抑えるということができません。
えっと思われるかもしれませんが実はどうしようもないことなのです。
人は「見られる」ことでストレスがたまり自律神経が反射的に動き交感神経が活性化して動悸や心拍数が上がるのです。天敵が目の前にたくさん現れた野生動物も同じです。自分の身を守るための防衛本能として、心臓がドキドキ口から飛び出そうになるのです。
人前にでるとドキドキするのはこのメカニズムです。この緊張状態は人間の生理現象ですのでどうやっても抑えられません。そして多くの人が「緊張している自分はダメなやつ」と自分を否定する捉え方をします。
しかしプロは違う捉え方をします。
ズバリ「緊張」を「集中するチャンス」と捉えるのです。
どんなプロの表現者でもプロスポーツ選手でも緊張をしない人はいないのです。逆に緊張しないと集中ゾーンに入れません!健康心理学者のケニー・マクゴニガル教授は緊張は自分の潜在能力を発揮するための引き金と言っています。
緊張とは仲良く手をつないで付き合っていくのが大事なのです。
ではどうしたら仲良く緊張と付き合い緊張を集中に変えることができるのでしょうか?
今日は、3つのアイデアをお伝えします。
【19分動画セミナー:緊張を克服する5つのポイント】
【1】徹底的な準備をする
想定できるスピーチのシチュエーションの場合、当たり前のことですが準備を徹底的にすることで自分自身の中で成功のイメージをつくることができます。
準備不足で本番に臨む人は以外と多いです。
私は、今でも講演前は前日からイメージづくりをします。
・立った状態
・お客さんの客層
・その場の空気感
・もっとも伝えたいキーワードは?
・締めの言葉
すべてをイメージするのです。イメージ力の準備不足が緊張を生みます。しっかりと成功のイメージを繰り返すことが心理状態に大きな安定をもたらすのです。本番時の動揺が少なくなります。
プロはイメージングの力をものすごく大切にしているのですよ。
【ベストなスピーチの時間は?】
ベストな時間は?惹きつける乾杯スピーチのコツ
【2】意識のベクトルを自分から相手へ
緊張を引き寄せる悪い呪文の一つが
「失敗したらどうしよう」
「周りからどう思われるだろう」
「評価が下がったらどうしよう」
です。
これは思考のベクトルが自分向きになっている証拠です。
あなたの話を聞く人には関係のないことです。人は自分にベクトルが向いている時に緊張します。ですから意識を聴衆に向けるのが緊張をなくすために重要な事です。
「聞く人にこんなメリットを届けたい」
「私の話で喜んでもらいたい」
と外向きにベクトルが向くだけで人間は心理的に“私に共感して欲しい”という気持ちが生まれます。登壇がワクワクするものになるのですよ。これがこちらの”プレゼンで緊張しなくなるための秘訣3″という記事でも紹介している原則「なぜその場にいるのかを考える」です。
そもそもなぜその場に登壇するのですか?毎回毎回原点に還りましょう。
「いやだなぁ」ですか?
「当たり障りなくはやく済ませよう」ですか?
自分がその場に存在する意義を自分に問いかけるのです。
そしてドキドキしてきたら「よし集中するチャンスが来た!」と肯定的な思考に変えましょう。一時的な緊張というストレスは自分を成長させ、幸せと繁栄への入り口だと前述のケニー・マクゴニガル教授は科学的にも証明しています。
【3】緊張克服は場数、場数、場数
やはり「場数」がある人は強いと言えます。少し投げやりな言い方と思う方もいるかもしれませんが、上記の【1】と【2】を知って場数を踏むのと踏まないのでは大きな違いを生むものです。
先日私は子供向けの講演を行いました。大人向けの講演と違って、自制意識がまだ弱い子供向けの講演はまだ経験が薄いために尋常ではないほど心拍数があがりました。しかし私より年齢の若い講師仲間が「佐藤さん、大丈夫です。場数ですよ。」とリラックスした顔で言っていました。
まさにその通りですね。
そしていつものように自分に問いかけました。意識のベクトルを自分から相手へ向けるために「何のために来ているのか?」と。
そしてこちらの”プレゼンで緊張しなくなるための秘訣2〜呼吸編〜という記事でも紹介している方法で自分の呼吸を整え、緊張を集中に変えました。
人前で何度もスピーチすることに挑戦し改善を繰り返している人はスピーチするための心の器が大きくなり自然と上手くなるものです。
場数に勝る先生なしです。それが突然振られたシチュエーションでの心の余裕と対応力も生み出します。
場数は3桁踏めば、確実に緊張を克服できます。
1桁の経験はどんな人でも緊張するものです。2桁の経験でもまだ足りません。目標は3桁の経験。3桁の経験を持てばまちがいなくあなたは、緊張を乗り越えるだけでなく、人前でスピーチをする達人になるでしょう。

3)共感や賛同を得るためのスピーチのコツ5選
スピーチのコツはたくさんありますが、やり方ばかりに注力してもいけません。聞き手の共感や賛同を得て心を動かすことがスピーチの最大の目的です。ここからは私なりのコツを、ピックアップしてご紹介します。ぜひ手帳にメモなどして見返し自分のスキルアップの材料にしてください。
スピーチのコツ1:”For you”の意識を根底に持つ
スピーチで気をつけることは自慢になってはいけないということです。自分ではそんなつもりはなくても聞き手に「だから何?」と感じさせてしまった場合は自己満足で終わってしまいます。
そうならないために根底でしっかりと腑に落としておかないといけないスピーチの心構えはFor me(私のため)ではなくFor you(聞いている人のため)という意識です。スピーチの難しいところは主観(私のため)になりやすくなってしまうことです。
スピーチとは何かしらのメッセージを聞き手にプレゼントすること。スピーチを通して聞き手のなかで
「よし、わたしもがんばろう」
「背景にはそんな逸話があった事を知り感動した」
「(あなたのスピーチで)みんなの前で承認してもらえた。このイベント企画をやってよかった」
など心にプラスの感情を促して初めて、大きな成果がうまれるでしょう。
そのためにはスピーチする際に「何をプレゼントできるか?」というFor Youの心構えが根底にある人とない人では大きな差が産まれます。スピーチのコツ1として、必ずこの原点に立ち返りましょう。
スピーチのコツ2:スピーチの基本構成を理解しておく
全体像を見ながら目の前の物事に向き合い、タスクをこなしていく人と、全体像を把握せずに目の前のタスクに追われている人では仕事の成果に大きな差が出ます。
スピーチも似ていて、全体像を捉えている人は上達が早いです。
全体像として一般的なのが
「つかみ」
↓
「本題」
↓
「オチ」
という話の流れです。これは一般的に共通している基本構成だと思います。
「つかみ」とは、聞き手に「この話は面白そう!」と思わせることです。共感や賛同を得られるスピーチにするためにはつかみで一気に聴衆の心を掴んで世界観に巻き込んでいくのです。(つかみの作り方についてはこちらの”つかみづくりの7つのポイント”という記事を研究してみる事をおすすめします)
「本題」とは、スピーチで一番伝えたいメッセージの中身です。
「オチ」とは聞いた人の背中を押すような言葉や締めの自分の展望や意欲の表示(コミットメント)です。
スピーチをするうえで、この全体像を必ず理解して構成を練りましょう。経験を積むと、急に振られた際のスピーチでもこれができるようになってきます。もし急に振られてこの全体像が思い浮かび、うまくいった際は、タイトルにもあるようにスピーチ後の気持ち良さを感じるでしょう。
ちなみに日本の芸術文化の落語はほぼこの構成です。詳しく知りたい方はこちらの“落語から学ぶ人の心をつかむプレゼンの極意”という記事を参考にお読みください。
スピーチのコツ3:体験談を入れて共感を得る
スピーチでは一方的に持論を押し付けると、参加者に抵抗感を持たれてしまいます。実際にどんな経験や体験をしたのかを紹介することで具体性やオリジナリティがうまれ参加者の共感を得ることができます。
積極的に体験談をいれましょう。
私がお勧めするのがEAT-innの法則(勝手に命名しました)です。
EはExperience(経験)のE
AはAwereness(気づき)のA
TはTheory(セオリー)のT
です。
innはオチに繋げましょうという意味です。
本題で惹きつけるスピーチのコツはまず内容に紐付けた自分の経験やストーリーから話すのです。
例えば「先日、私は産まれて初めて落語を見に行きました、こんなに面白いものかと一日楽しみました。誘ってくれた○○さんに感謝しています。ありがとう。(Eの経験)
→その時に、落語は、人前で魅力的なスピーチする時にとても役立つという事に気づいたいのです!(Aの自分の気づき)
→○○さんから落語の基礎は聞いていました。落語にはまくら(つかみ)→本題→オチという基本構造があるそうです。確かにプロの落語家の話は皆さんその構成に乗っ取っている。(Tで説得)
→皆さんがスピーチする時にとても勉強になります。ぜひ一度寄席に足を運んで学んでみてください。きっと大きな気づきが得られますよ。(inn:オチ)」
自分の実体験が先にきているので話にリアリティや説得性がありますよね。人は経験談やストーリーに共感するものなのです。とくに失敗談や挫折を乗り越えた話は効果的でしょう。
スピーチのコツ4:暗記しない!
スピーチの際、頭が真っ白になってしまったことはありませんか?私自身も経験がありますし真っ白になってフリーズしてしまった方もたくさん見たことがあります。
なぜ真っ白になると思いますか?
その理由はズバリ“話す内容を丸暗記して”伝えようとしているからです。
途中でつまって次のフレーズが思い浮かばなくなり次なんだっけ?次なんだっけ?とパニックになり自分で何を話しているかわからない状態に陥ります。
先日私は、ある上場企業経営者のプレゼントレーニングをしました。その経営者の方はプレゼンに非常に苦手意識を持ち恐れている方でした。この経営者の方は毎回原稿を用意し最初から最後まで一生懸命暗記して登壇していました。
会社のトップが社員の前で失敗を晒してすくんでいる姿を見せるのは精神的にも辛いものです。しかし止まって頭が真っ白になった過去がありそれがトラウマになっているとおっしゃっていました。
はっきり言いまして本番直前に原稿の丸暗記なんて劇団四季の俳優でも無理です。
暗記はやめましょう!
いいことはありません。
ではどうしたらいいのか?
それが、コツ5の「ゴールに結びつける」です。
スピーチのコツ5:全てはゴールに紐づける
例えば、マラソンはゴールがないと彷徨いますよね。カーナビは目的地を設定しないと機能しません。あなたが会社から自宅に帰宅する時無意識に足が自宅に向かうのは、自宅というゴールがあるからです。
スピーチも同じです。皆さん、ゴールがないから彷徨うのです。何を言っているのかわからなくなるのです。暗記して真っ白になるのです。
このコラムを書いている私はつい先日も突然3分程スピーチしてくださいと無茶振りをされました。そういう時はすぐに目的を考えます。そこからゴール(コアメッセージ)を定めます。そこに向けて進んでいくのです。
「あなたがこのスピーチでもっとも伝えたい事は?」
「あなたが一番伝えたいメッセージをキーワードで表すと?」
「最終的にスピーチを聞いた人がどうなったらいい?」
これを理解してゴールに向かって簡潔に堂々と進んでいけば、敵に怯えた子鹿から攻めるライオンのような心理状態に変われますよ。暗記しないとコツ4で言いましたが、暗記するとしたらゴールに紐づけるためのキーワードを2〜3個です。
コツ3の共感や賛同を得るための具体的なストーリーの作り方を知りたい方
コツ4の暗記をしない!!をもう一歩深く知りたい方
コツ5のゴールを設定してキーワードを紐付けて進んでいく
を詳しく知りたい方は、こちらの“スピーチの素人が1000名の前でも堂々と話せるようになるプレゼン研修とは?”という記事をご熟読ください。

4)スピーチに関するその他のQ&A
ここまでスピーチのコツを紹介してきましたが、スピーチを前にまだまだ不安だという人もいるでしょう。ここでは、もっと聞いておきたいという方の疑問や不安解消策についてお答えします。
【Q1】目線や身振り手振りはどうしたらいいですか?
身振り手振りなどボディーランゲージといったテクニックを重要視しその手法を学ぼうとする人や教える講師はとても多いですが、一足飛びにそこまで身につけようとする必要はありません。むしろ余計な動きや無駄なジェスチャーを削ぎ落として何もしないくらいを重要視しましょう。録画して自分のスピーチを見てみるとわかります。
自意識がうまれて不安を解消するために無駄な動きをしていることがよくわかるでしょう。こちらの“スティーブジョブズのプレゼンを真似て「イタい人」にならないための豆知識”という記事は無駄な動きがどれだけ不自然かがよくわかる記事ですのでご覧ください。
【Q2】話に引き込むコツは他にどんなものがありますか?
導入でつかみ、インパクトを与えることは紹介しましたが、私は第一声の大きさも重要だと思います。私はプロの舞台の世界で活きてきましたが、つかみの第一声が弱いとすべてが終わります。逆に第一声をしっかりとした声で放つとスッと落ち着いたりするものです。
声を出すためには深い呼吸を聞き手に意識することが重要です。
こちらは動画で解説しておりますのでぜひご覧ください。
★呼吸の基礎「吐ききって脱力」
★プレゼンの基礎「息の支えとは?」
★呼吸と声のトレーニング(音声版)
【Q3】スピーチ前日に緊張しないためにはどうすればいいですか?
繰り返しますがスピーチに慣れている人でも前日は緊張します。決して「緊張している自分は情けない」などと決して思わないで下さい。
具体的な対策としては、徹底的な準備のところでお伝えしたイメージトレーニングをするのと同時に、実際に声を出してみるということをおすすめします。聞き手や参加者全員の様子をイメージして、暗記するのではなく、ゴールとキーワードを紐ずけて、つかみ→本題→オチの基本構成に乗っ取って繰り返し練習してみるのです。
失敗して止まってしまっても自分を責めないでください。当たり前のことです。何回も何回も声を出すことにより脳と身体が潜在意識に言葉を記憶して本番でスッとキーワードなどの言葉が出てくるものです。
本番では、すべてを捨てましょう。練習と全く違うことを話してしまうことも多々あります。しかしゴールが定まっていれば問題ありません。そうやって経験を積んでいくのです。
まとめ
皆さんは、今回紹介したスピーチのコツを参考に経験を積み重ねてください。そしてなんども本番に臨んでみてください。経験を積み重ねれば、あなたのスキルはどんどん高まり、気持ちよく話せるようになるものです。
運転免許証をもっていれば運転も徐々に怖く無くなっていきます。公道に出たばかりの時はみんな怖いです。しかし免許を持っていれば経験になります。
多くの人が「免許を持たないで公道に出る」つまりスピーチのコツ5選を知らないまま人前に立つからいくらやっても怖いのです。一緒に乗っている人も見ている周りも本人も、みんな怖いです。
この記事を通して気持ちのいいスピーチをするための考え方・捉え方(免許証)を身につけて経験を積んであなたの価値を高めてくださいね。
【関連記事】
スピーチの素人が1000名の前でも堂々と話せるようになるプレゼン研修とは
<参考文献>
【コトバンク】
【アサヒホールディングス】
【経団連】
この記事の筆者に研修に興味をもった方はこちらからお問い合わせください。
筆者の3分講師紹介動画
筆者:佐藤政樹のプロフィールはこちら。
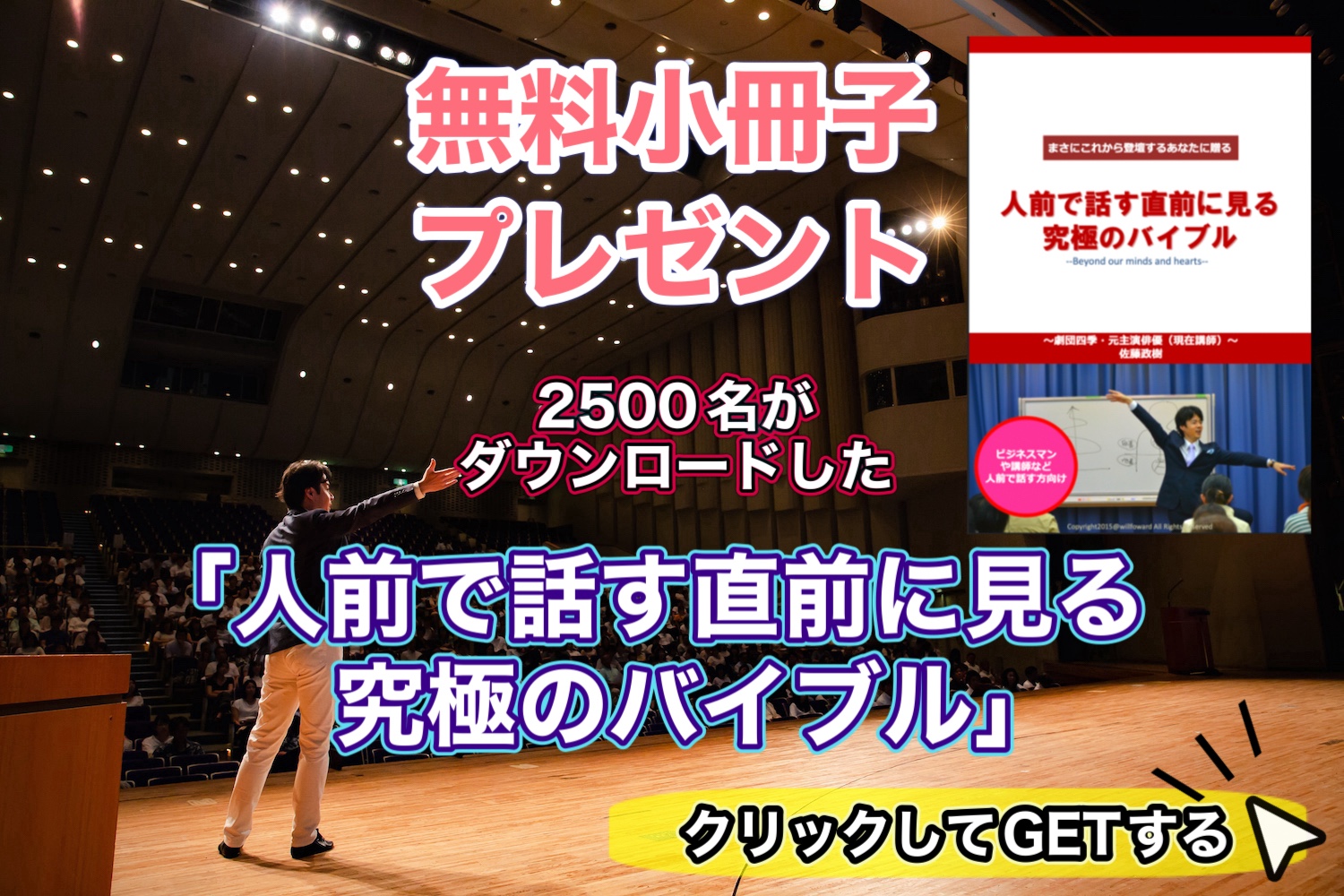 「人前で話す直前に見る究極のバイブル」
「人前で話す直前に見る究極のバイブル」
・なぜ、人は感動するのか?その表現の本質
・人前で話す人は必見の伝達力を高める5つの原則
・うまく話せなくても伝わるのはなぜか?
など人前で話すビジネスパーソンに役立つ情報満載です。
無料ですので、ぜひダウンロードしてください!!
SNSでも発信してます
Follow @masakisatochan

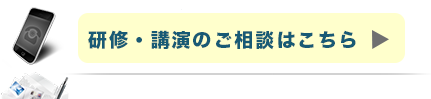
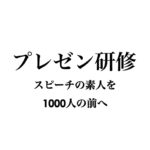

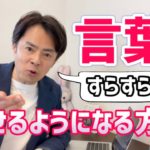


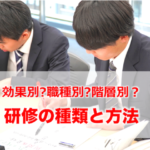 2024年4月23日
2024年4月23日
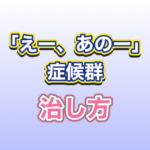 2024年4月20日
2024年4月20日
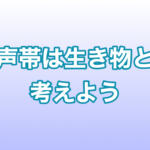 2024年4月6日
2024年4月6日
 2024年4月5日
2024年4月5日